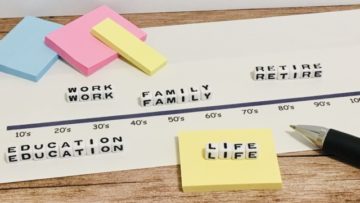学び直しには、言葉の定義がいろいろあります。
「リスキリング」「リカレント教育」「アンラーニング」です。
それぞれは学び直しに関する用語ですが、意味が異なります。
そこで、それぞれの意味について説明したうえで、どのように学ぶことがキャリア成長に繋がるのかをお伝えできればと思います。
学び直しはなぜ必要?

学び直しには、学び続けることで人生を豊かにする目的があります。
また、学び直しに年齢は関係なく、何歳からでも可能です。
学び直しが注目される背景として、先行きが見えない不透明な時代、更には人生100年時代があります。
終身雇用制度の崩壊により、定年まで同じ会社で働き続けられる保障がなくなっています。
また、100年生きる時代になり、定年後の人生も長い。
会社が自分のキャリアの面倒を見てくれる時代ではなくなり、自分の人生は自分で切り開く必要があります。
変化が激しい世の中では、情報の更新も早く、同じ知識、スキルのままでは通用せず、常にアップデートしなければならなくなりました。
学び直しは時代の変化についてゆくための、必須作業になりつつあります。
半面、学び続ける意識と行動次第では、自分のやりたいことや夢が叶う可能性も高くなります。
また、思考を刺激し、いつまでも若々しくいるために学び直しは効果的でもあります。
学び直しの用語について
学び直しを意味する用語として「リスキリング」「リカレント教育」「アンラーニング」があります。
それぞれ、意味や視点が異なりますが、その意味を理解し、効率的に活用することで、効果的に学び直しを進めることができると思います。
では、順にみていきましょう。
リスキリングは企業や組織主体の学び直し

リスキリングは最近、頻繁に使われるようになった用語です。
学び直しといえば、リスキリングと世間では認識されるようになってきました。
リスキリングは業務の変化に伴う新しいスキルや知識の習得を従業員に対して促すことを指します。
つまり、企業や組織が主体となり従業員に学び直しを促します。
DX化などの環境変化の伴い、企業や組織が施策として、リスキリングを導入するケースが増えています。
個人から見ると、業務やニーズの変化に伴い、新しいスキルや知識を職場の支援下で学べるため、現職への適用のみならず、将来的な転職の際にも役立ちます。
リスキリングの代表例としてはITスキル、マーケティングスキル、データ分析のスキルです。
どれも昨今のDX化に伴い、必要性が高まっているスキルです。
エンジニアとして長年働いていても、「先進IT」のスキルを習得していないと市場で通用しない時代です。
また、企業がダイバーシティ(多様性)を推進しているなかで、コミュニケーション力を強化するリスキリングも注目されています。
英語などの語学力強化も、以前から各企業で教育施策が存在しますが、これもリスクリングの施策にあたります。
リカレント教育は個人が主体の学び直し

労働者の主体的な学びを意味します。
リスキリングとは違い、個人が主体となって取り組む学び直しです。
厚生労働省の定義では、「学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくこと」と記載されています。
個人的には「仕事」のみに捉われず、豊かな人生を送るために学び続けるといった視点がしっくりきます。
つまり、仕事をしている時だけに限らない学習なので、生きている限り学び続ける生涯学習の視点です。
仕事で通用する学び以外にも、趣味や自己実現の視点も交えて、自分自身がやってみたいことに対する学びもリカレント教育に含めるとキャリアの幅が広がると思います。
学び直しは給付金制度もある
リカレント教育は国が推進している事業でもあるため、支援制度があります。
代表例としては教育訓練給付金です。
教育訓練給付制度の適用講座は、以下の検索サイトより調べることができます。
・教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
学び直しのサイト
通信制大学や、大学が開講している講座なども学び直しに活用できます。
私も通信制大学で学んでおり、リカレント教育実践者です。
学生時代にはスルーしていたような科目や内容も、社会人経験を経てから見直すと、学習する意味が見いだせたりします。
「社会人になってからの学び直しは楽しい!」が私の感想です。
社会人の学び直しを紹介するサイトとして、マナパスやスタディサプリがあります。
(以下の紹介にはプロモーションが含まれています)
仕事と学びの両立は、勉強時間の確保など大変ではありますが、人生を豊かにするための手段だと思います。
通信制大学であれば、3年次編入で2年間学ぶ場合でも50万円もかからない大学もあります。(私の場合は50万円以下です)
アンラーニングは使えない知識、スキル、価値観を捨てること

アンラーニングは「学習棄却」と呼ばれます。
これまで学んできたものや、身につけてきたスキルのうち、つかえないものを捨て、新しく学びなおすことを意味します。
アンラーニングの特徴に、これまでの人生で学んできた「価値観」を見直すといった考え方があります。
「学びほぐす」と表現されることもあるので、こちらの方がしっくりきます。
なぜなら、アンラーニングには完全にこれまでの知識やスキルを捨てるわけではなく、これまでの成功体験などから定着している固定観念を変えて、変化に対応しようといった意味があります。
完全に捨てるわけではなく、使用停止状態にする感じです。
例えば、今までうまくいっていた手法や考え方のせいで、頭が凝り固まってしまい、停滞感を感じてしまうケースなどが、このアンラーニングが有効になってきます。
つまり、こだわりを捨ててしまうわけです。
アンラーニングが必要になるのは、転職、セカンドキャリア、異動などの転機で環境が変わる場面です。
また、現職であっても、組織変革、DX化による業務の変化、職場風土の改革、新規事業への進出などの際にもアンラーニングは効果的です。
アンラーニングが上手にできるようになれば、自分がこれまで培ってきた「強み」と市場や他者から求められているニーズ(売り)を使い分けることができるようになると思います。
なお、アンラーニングを進める際に重要となるプロセスに「内省(リフレクション)」があります。
自分の固定観念は自分自身では気付かないことが多く、キャリアコンサルタントなどと一緒に考える機会があると効率的です。
「当たり前」と思っていること、実はこれがアンラーニングの対象だったりするのです。
学び直しで収入が増える?
社会人になってから大学などでの学びを続けている人は、収入アップや正社員として登用される確立が高まるとの調査結果が内閣府から発表されています。(非正規⇒正社員への転換率が高まる)
・リカレント教育による人的資本投資に関する分析-実態と効果について(内閣府)
学び直しに積極的な人は、意欲が高いため、生産性の高い人材になりやすい点もあると思います。